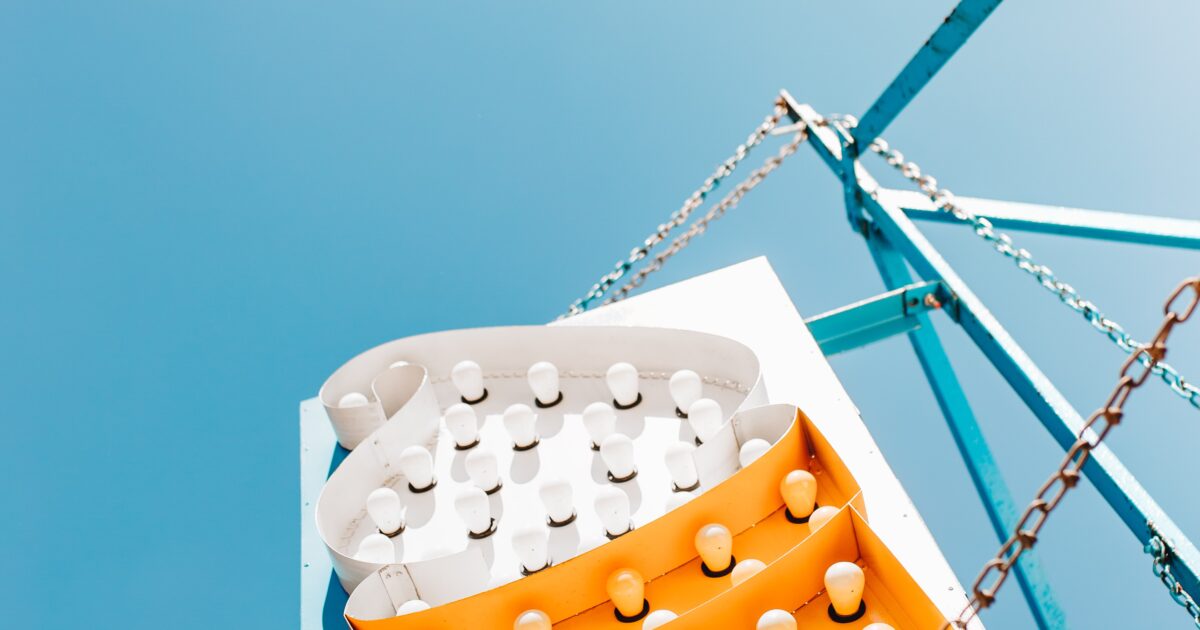"いまでも、ドライブしている時に山下達郎の「スパークル」がかかると、思わず歌ってしまいます"
「シティ・ポップ」という言葉を聞くと、ある年代以上は懐かしさを覚えるかもしれない。1970年代後半から、それ以前に広く聴かれていたフォークなどと一線を画すように、「都会的」で「おしゃれ」な音楽としてマーケットを席巻するようになった一群のポップスを、そう称していたことを記憶している人は少なくないだろう。それはまた盛り上がりつつあったバブル景気のBGMの役割も果たしていた(企業のCMなどにそれらの音楽が多用されていたことも大きかった)。ゆえにバブルが崩壊すると、シティ・ポップは急速に沈静化していく。ところが2010年代あたりから、またこの「シティ・ポップ」という言葉が、こんどはナイトクラブで活躍するDJなどから聞かれるようになった。数年前ヒットを飛ばした「Suchmos(サチモス)」のようなグループがシティ・ポップの現在形ともいわれ、この言葉とそこに括られる音楽が、いままた注目を集めている。

「この言葉がごく一般的に広まったきっかけは、あるTV番組で『タエコ・オオヌキのレコードを探している』と話した来日外国人旅行者を取り上げたことじゃないでしょうか。10年くらい前から、レコードが再評価され始めたことと、海外の人たちが評価し始めたことが、昨今のシティ・ポップの盛り上がりのもとになったと思います」
このように語るのは、クニモンド瀧口さん。自身のバンド「流線形」で現代のシティ・ポップブームの先駆けとなり、DJやプロデューサーとして新旧のシティ・ポップを紹介する仕掛け人でもある。もっとも、彼にとってシティ・ポップは自身の音楽嗜好の原点と繋がっている。

「DJをやる時は、いわゆる『和モノ(日本の音楽)』しかかけていません。初めてレコードを買い始めたのが小学生の頃だったのですが、近所に住んでいた大学生のお兄さんやお姉さんがおしゃれな音楽を聴いているのを知って、その中に山下達郎さんやユーミンが入っていたんです。そこから僕自身も聴くようになりました」
こう語る瀧口さんは、長じてレコード店のジャズ・バイヤーとなり、90年代にクラブミュージックが盛り上がった際、売り場に自身のコーナーをつくって、日本のレア・グルーヴとして和モノを紹介し始めた。当時はまだDJで和モノをかけると白い目で見られたというが、店頭では山下達郎の音楽などに反応する外国人も数多くいたという。やがて個人的につくっていた音楽を友人の薦めでリリースしたところ好評で、次第にシティ・ポップは注目されるようになった。

そんなシティ・ポップはドライブと密接な関係にある、と瀧口さん。
「僕が考えるシティ・ポップ像には、〝大人への憧れ〟からくる音楽という性格があって、それはまたドライブというシチュエーションがハマるんです。個人的な記憶ですが、小学生や中学生のときに、近所のお兄さんやお姉さんが海などにドライブに連れて行ってくれた際、車中では彼らが編集したマイ・カセットテープがかかっていて、そこに山下達郎とか吉田美奈子、ユーミンが入っていたんです。ドライブで、そういう音楽が流れるのがすごいかっこいいなと感じました。別の日には六本木に行こうとお兄さんの車で高速に乗った時、マーヴィン・ゲイの『ミッドナイト・ラヴ』とかドナルド・フェイゲンの『ナイトフライ』とともに、角松敏生の『ゴールド・ディガー』が流れていました」
こうした原体験はなかなか更新されませんね、と瀧口さん。さらに憧れをバックボーンとした都会感が、シティ・ポップの特徴であるとも。そして、そんなシティ・ポップとは時代とともにアップデートされていくものという。
「単純に山下達郎さんをベースに同じような音楽をやっていてもあまり発展性がなくて、自分の親が山下達郎を聴いていたとして、じゃあ自分たちなりに音楽をやってみようとヒップホップの要素を入れてみたり、ジャズの要素が入ったりとかすることで、音楽として面白い化学反応を起こしていくんじゃないかと思っています」
DJ / プロデューサー クニモンド瀧口

レコード・バイヤーなどとして働く傍ら、DJ として活動。趣味でつくっていた音楽が認められ、2003 年に流線形としてデビュー。菊池成孔や故・川勝正幸といった識者から評価された。またプロデューサーとして、一十三十一(ひとみとい)やナツ・サマーといったアーティストを手がけている。